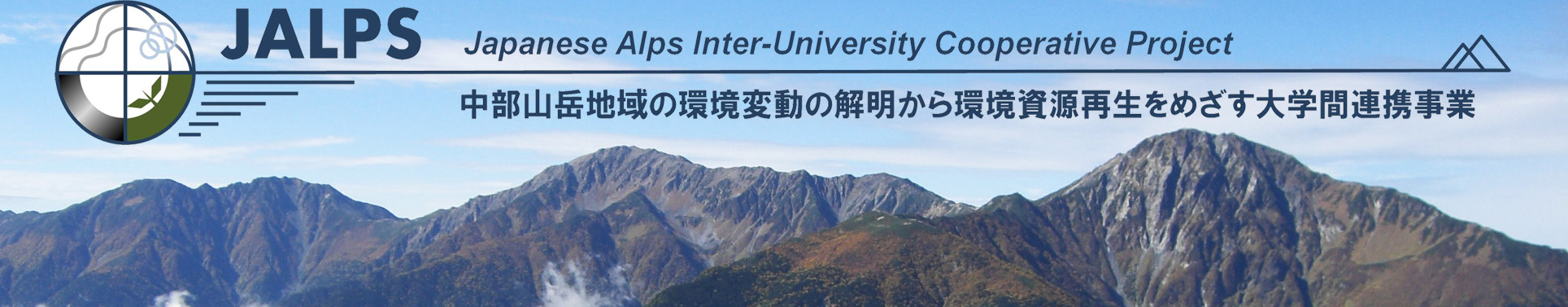■ 炭素循環変動研究グループ
このページは、「地球環境再生プログラム」平成22年度事業報告書より抜粋して、作成しています(2011.5.31現在)。
1.研究の背景
今日、地球温暖化などの環境変動が危惧されていて、陸域生態系にも影響が及ぶと考えられる。とくに山岳地の生態系は脆弱で、環境変動の影響を受けやすいと指摘されている。一方、炭素は物質循環のもっとも重要な構成要素であり、植物が光合成によって固定するが、大気中に排出される温室効果ガスの主要な成分である。このため植生をモニタリングして炭素の動態を把握するとともに、炭素動態に温暖化が及ぼす影響を評価することが重要である。
2.研究目的
このような背景から、陸域生態系における炭素循環の実態を明らかにすることを目的として、 地上観測を実施して、炭素循環プロセスのパラメータ化や既存モデルを介したスケールアップの手法を開発する。また、土壌呼吸の温度依存性について検証し、生態系への温暖化の影響予測の可能性を検証する。炭素収支を適切に評価するには生態系内にとどまらず、人為的な活動に由来する炭素収支を評価する必要があるため、木材利用における炭素収支を明らかにすることを目指す(図1)。このため以下のような研究目標を設定した。
1. 広域での炭素収支評価のための基盤技術を確立する。
2. 環境要因と土壌呼吸の関係を明らかにする。
3. 川上・川下の木材流通の中で、炭素収支を明らかにする。
さらに本事業において人材を育成するために、学生を研究に参画させて技術・知識を習得させること、成果の周知を図るために講義や成果報告会などにより、得られた成果を学生や住民に広める。
3.研究内容
以上の目的を達成するために、以下のような研究を実施する。
1. 炭素収支の実態を継続して観測する。
バイオマス、純一次生産量、葉面積指数、光合成、土壌炭素・土壌呼吸、炭素固定量
2. 諸量の特徴を解析し、パラメータを整備する
土壌呼吸の特徴を解明する(植生タイプ、標高、温度依存性など)
窒素やリンの濃度と土壌呼吸の関係を明らかにする
3. 葉面積指数(LAI)の分布を推定し、LAIを介してスケールアップを行う。
4. 木材のライフサイクルアセスメントにより、木材利用サイドの炭素収支を評価する。
4.グループ内外の連携
炭素循環グループでは連携の第1ステップとして方法論を進化させることを目指す。グループ内で観測している8箇所のサイトで、脆弱な山岳生態系について総合的な観測態勢を構築するため、炭素循環に関する測定プロトコルの統一を目指す。
この連携により、1)相互に基盤技術を共有(測定法の共通化)することで、データを均質化し、相互比較を容易にし、2)炭素循環に関する知見を集約することで、土壌呼吸の環境応答が明らかにし、3)モデルへ入力するパラメータを整備し、スケールアップの基盤技術を強化できることが期待される。
また、他グループから提供される情報・データにより研究を発展できると期待される。例えば広域の炭素収支マッピングには気象データが不可欠であり、気候変動シナリオや生態系変動シナリオが提供されれば、気候変動に対する炭素収支の変化をマッピングに繋がる。
5.次年度の計画
次年度の研究計画は概ね次の通りである。
土壌:
1. 今年度の観測の継続
2. 土壌呼吸測定のデモンストレーションを行って、知見と技術の共有を目指す。
3. 根呼吸と従属栄養生物の呼吸の分離した測定
4. 枯死木・倒木の定量化および枯死木分解に伴うCO2放出量の評価
5. 微生物活性のリンと窒素の制限について検討する。
6. 落葉広葉樹林流域と人工林流域の渓流水へのDOC流出量について
LAIマッピング:
1. Landsat/TMデータを利用したLAIマップの試作(2000年6月分の予定)
ライフサイクルアセスメント:
1. 南信のヒノキ林を対象にライフサイクルアセスメントの調査を行う。
また、温暖化の影響予測を考えると、様々な環境要因に対する応答特性検証のための実験などが必要で、例えばインキュベーター等を用いた実験的検証が今後の検討課題である。