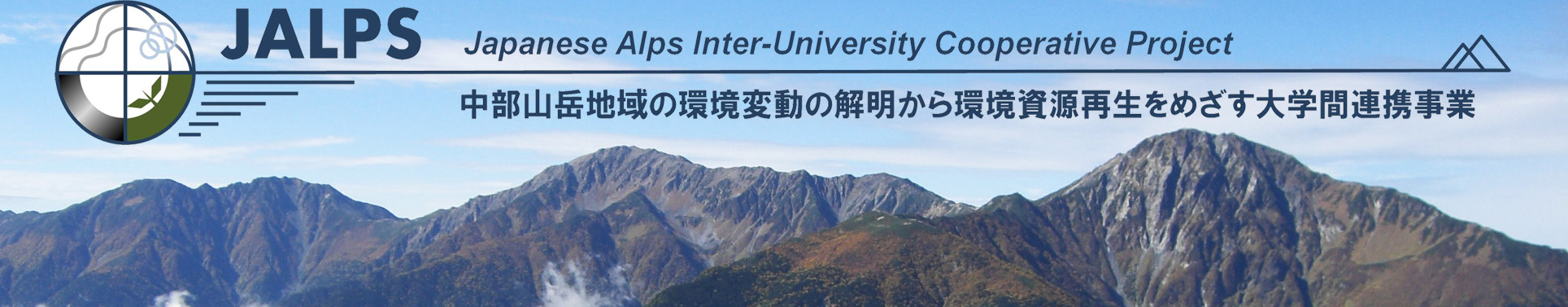■ 気候変動研究グループ
このページは、「地球環境再生プログラム」平成22年度事業報告書より抜粋して、作成しています。
1.研究目的と研究組織について
気候変動研究グループは,10名余の小規模な集団でありながら,山岳気象学,衛星生態学,生物気候学,水文学,湖沼学,自然地理学,古気候学および気候モデリングときわめて多様な構成となっている.そのため,各大学および各研究グループのもつ課題や実情を尊重しつつ,情報の交換と気候モデリングを軸とした協力体制をとることとし,以下のような研究の目標と課題を設定した.なお,これらは2010年12月18日の午前に後述するようなミニシンポを開催し,また,同日午後の気候変動グループでの議論を経たものである.
<研究目標>
中部山岳地域において,最終氷期最盛期から現在,さらには100年先までの気候変動を流域単位程度の精度で解明し,将来に起きうる地形や動・植物生態の変化,人間活動への影響を評価して,自然環境の保全の方策を明らかにする.
<当面の研究課題>
1) 中部山岳地域の「現在」の詳細な気候情報(観測値)の集積・整理・統合
山岳気象観測,衛星生態学,他分野・他研究機関などの協力でデータベース化
2) GCM気候モデルのスケールダウンによる高空間分解能の気候シミュレーション
予測地域と解像度,対象時期,重点項目の選択・設定
3) 高時間分解能(精度)の古気候情報の集積
古気候学:湖沼堆積物に記録されるプロキシーに限定,数値情報への変換
4) 数値モデルを利用した現象の診断と統合評価分析
<参加メンバーと研究分野:外部の協力者・サブメンバーを含む>
上野健一(山岳気象),鈴木智恵子(気候モデラー),植田宏昭(気候変動解析・モデリング),池田 敦(寒冷地地形学),公文富士夫(古気候学),原山智(山岳地形学),河合小百合(花粉分析,古植生学),朴虎東(湖沼生態学),安江 恒(年輪年代学),村岡裕由(衛星生態学),玉川一郎(モデリング解析),斎藤琢(生物気候学),児島利治(流域水文学)
2.H.22年度の活動報告
6月11日のキックオフ・ミーティングでは公文が気候変動グループの概要を紹介し,10月16日に信大西駒演習林で開催された研究集会では上野が気候変動グループの活動状況と方針を説明した.
2010年12月17日(金)の午前中に気候変動グループのミニワークショップを開催し,15名の参加を得て,以下の課題で研究発表が行われた.これらの発表を踏まえ,総合討論で研究計画等の議論を行った.また,12月17日午後の研究報告会では,本研究グループから11件のポスター発表があり、活発な討議が行われた.
公文富士夫(信州大):ワークショップの趣旨説明
上野健一(筑波大):冬期天候変化と極端現象の把握に向けて
鈴木智恵子(筑波大):中部山岳地域を対象とした将来気候のダウンスケール
植田宏昭(筑波大):気候モデル・プロキシおよび温暖化・古気候研究の接点
村岡裕由・斎藤 琢(岐阜大):高山サイトを核とした衛星生態学的研究による森林生態系機能の時空間分布評価の試み
公文富士夫(信州大):中部山岳地域の古気候情報の収集と解析の現状と課題
原山 智・河合小百合(信州大):上高地ボーリングから判明した地形発達史と山岳の環境変遷
安江 恒(信州大):年輪情報を用いた気候復元・成長変動予測
3.H.22〜23年度および今後の課題について
1) 中部地域における気候モデル検証・分析に資する観測データの収集と共有化
H.22年度からH.23年度の取り組みとして,標記の課題をあげ,メタデータの収集を行った.共有するためのデータフォーマットの作成や,データポリシーを議論し,ガイドラインを策定することにもなった.それを受けて,2011年3月に原案を作成した.
2) 今後の方針について
議論の中で出された意見は以下の通りである.
* 3つのランク(例:フリー,グループ内,許可,メタデータ)でデータを分類して利便性を高めることが必要.
* 中部山岳地域のデータ収集は3大学から開始し,他機関へ広げる.
* 「現在」という認識すら,対象や課題で違う.20年や50年先の「予測」には過去数十年が重要.年輪からの情報はないか.
* 計算機能力とコストの面から,time-sliceでならば過去のいろいろな時期のモデル化は可能.
* スーパーサイトにおける生態分野の情報を面的に広げるにも,モデル化は不可欠.気候モデルとの連携を探りたい.何をしたいか,という目的が重要で,それにより研究手法も変わる.
* 欲しいデータの例:高山植生の分布データ,積雪状態(融雪期),プロキシーデータ,1600年前以降の気温・環境データ
* 情報の共有 グループ内:Jalps内でのForum機能の利用
グループ外:運営委員会へ要望
* 要望を受ける仕組み
グループ長が相談して決定をする.または,情報を流して,個別に対応する
* ホームページの活用と充実
研究目的,活動状況,人的資源の拡大を目指す.
4.気象データアーカイブについて
3大学の管轄する観測拠点における気象データを2006-2010年の期間アーカイブし、平成24年度から部内でデータ公開を開始した。
詳しくは、JALPS気候変動グループ気象データ―アーカイブ(http://www.geoenv.tsukuba.ac.jp/~jalps-atm/index.html)を参照の事。