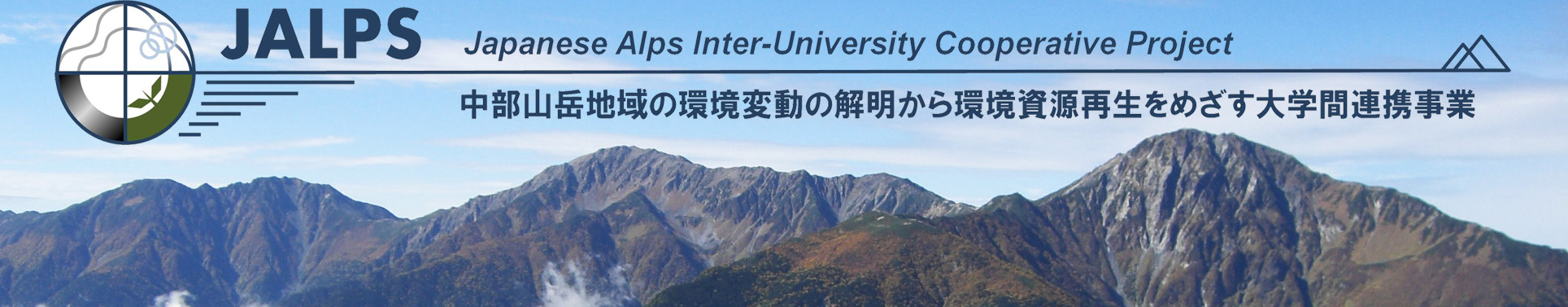■ 生態系変動研究グループ
このページは、「地球環境再生プログラム」平成22年度事業報告書より抜粋して、作成しています(2011.5.31現在)。
1.研究目的と研究手法の設定
生態系変動研究グループは,現在約30名のメンバーが参画し,各自の研究分野や手法は多様性に富んでいる.そのため研究機構立ち上げ以前の合同セミナーや研究会での議論をふまえて, 2010年10月16日に信州大学農学部で行われた研究会において,以下の2つの研究目的を設定することを確認した.
A1 中部山岳地域における生態系の変動を解明
A2 生態系資源の再生
さらにこれらの研究目的を達成するため,次の3つの研究手法で実施することが合意された.
B1 生物多様性減少のホットスポットでの調査
B2 標高傾度と群集・生態系の調査
B3 温暖化実験
2.各メンバーの研究の位置づけ
この研究会において,各メンバーが現在の研究テーマと内容を発表し,確認した研究目的と3つの研究手法に沿って多様なメンバーの研究の位置づけを整理した.その結果,表1のようにとりまとめ研究連携の枠組みを確認した.
その中から,研究手法に注目して以下のような連携研究テーマがピックアップされた.
(B1生物多様性減少のホットスポット)
3つのモデル地域(アルプスのお花畑,南アルプス:仙丈ヶ岳,中央アルプス:駒ヶ岳,北アルプス:槍・穂高)を設定し,空中(リモートセンシング)と地上(実地調査)から,高地生態系の生物多様性の実態を把握し,さらに温暖化など環境変動による生態系の各要素(動物,鳥,昆虫,土壌動物,樹木,草本植物,菌類など)の影響を解明する.
(B2標高傾度と群集・生態系の調査)
指標種指標種群による中部山岳域の環境変動(温暖化)のセンサー手法の開発
群集レベルで垂直分布と生物多様性の関係を調査.高山チョウ:北アルプス(徳沢〜蝶が岳),仙丈ヶ岳三峰川流域,地表性歩行虫:信州大学農学部西駒演習林と仙丈ヶ岳を含む南アルプス,植生調査・地衣類:西駒演習林.
標高傾度にそった種レベルの変異を調査.コクロナガオサムシの亜種:南アルプス,遺伝子レベルと標高傾度の関係,ミヤマハタザオの標高適応遺伝子の解析
(B3温暖化実験)
森林限界(ハイマツ帯とシラビソ帯の境界)で温暖化実験:信州大学農学部西駒演習林でハウスを設置して実施.調査項目 樹木・草本,菌根菌,分解菌,土壌呼吸,土壌動物など
3.平成22年度の研究成果の発表と検討
2010 年12月17日に筑波大学で行われた年次研究報告会において,生態系変動研究グループは25件の研究発表があり,グループミーティングで位置づけの再検討が行われた.その結果,研究手法としてあらたに環境応答の枠を加え,研究対象に個体レベルを追加して4×4の枠組みで研究連携と情報共有を測ることになった.
また生物多様性ホットスポットにおける植物群集の研究分野や標高傾度に関する群集から遺伝子レベルまでを包括する研究など,当グループの研究分野の特徴が明らかになった.
4.次年度以降の課題
次年度以降の課題として,ミーティングの中で以下の点が上げられた.
*他のグループと連携を図る.特に炭素循環グループと連携を具体化する点.
*第2の研究目的である生態系環境資源の再生に関しては,対象を人間に限定しないで,山岳域の絶滅危惧種,生物多様性の保全・保護,獣害対策(シカの食害),リモセンを利用した森林管理と生物多様性をテーマに研究を進める.
*その他,ホットスポットでの集中研究,資金の獲得などの課題が検討された.