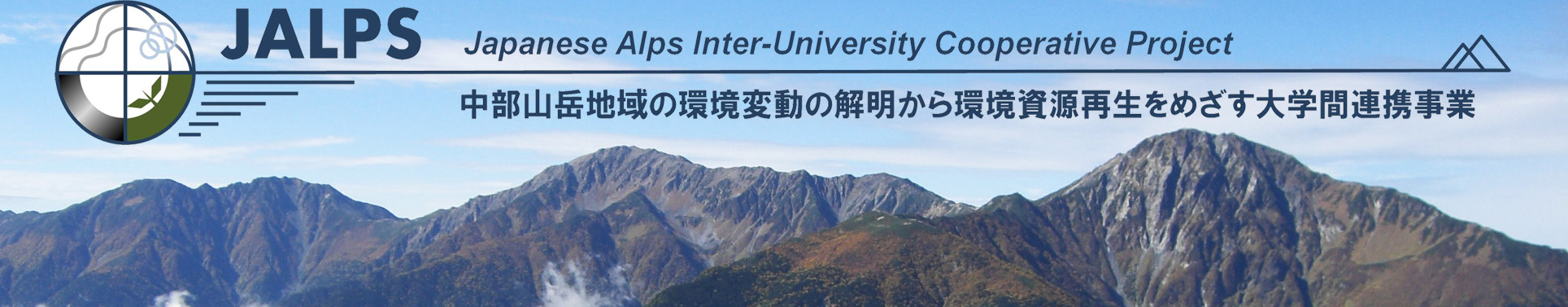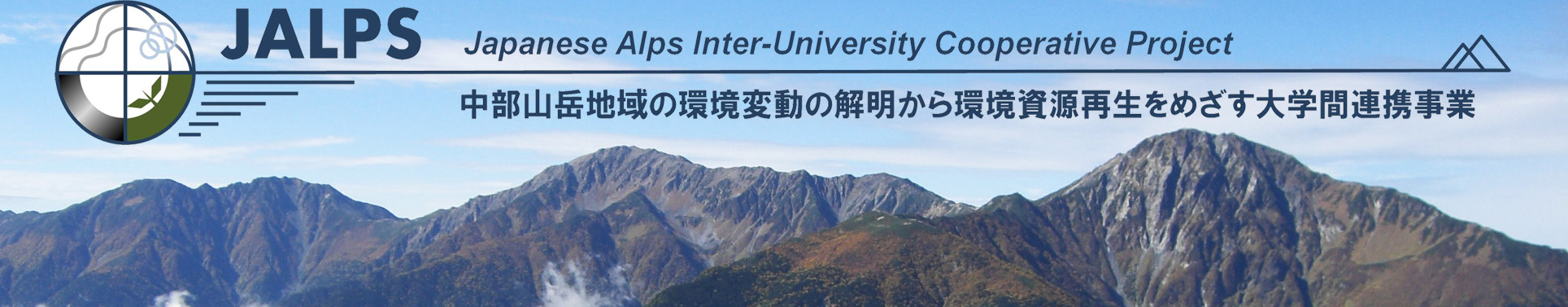








トップ >
プロジェクト>
研究グループ>
<水循環・物質循環変動研究グループ>
■ 水循環・物質循環変動研究グループ
水循環・物質循環変動研究グループ構成員
グループ長:松岡憲知、副グループ長:今泉文寿
筑波大: 松岡憲知、浅沼 順、山中 勤、辻村真貴、田中 正、今泉文寿、関口智寛、トーマス・パークナー、池田 敦、岩上 翔、若狭 幸、脇山義史、西井 稜子
信州大: 鈴木啓助、北原 曜、宮原裕一、小林 元、小野 裕、佐々木明彦
岐阜大: 藤田裕一郎、李 富生、沢田和秀、児島利治、山田俊郎、魏 永芬、大西健夫、廣岡佳弥子
(27名 2011.4.1 現在)
背景
(水循環とは)
水は生命の源であると同時に、我々の生命・財産を脅かす存在でもあります。湿潤多雨の気候下にある我が国では、降水および降雪によってもたらされた水が山体やその上に生育した森林によって涵養され、われわれの生活圏に上質な水資源を安定供給してきました。一方で、集中的な豪雨や融雪によって、急峻な山地において洪水や土砂災害を引き起こしてきました。水の脅威を排し、その恩恵を享受するために水循環を理解することは不可欠であるといえます。
(物質循環とは)
水によって輸送されるさまざまな物質の行方を知ることも重要です。源頭部における斜面崩壊にともなう土砂流出は河川の河床変動やダムの堆砂などの流砂系の問題を引き起こします。また、硝酸態窒素や人為期限の化学物質などは河川を通じて、我々の住む都市域に流入し、健康被害のリスクを高める可能性があります。このように水によって媒介される物質循環を解明することは、われわれの生活に直結する課題です。
(地球温暖化の影響)
地球温暖化とそれにともなう気候変動は、こうした水循環・物質循環の在り方を変化させようとしています。IPCC 第4次評価報告書では、日本では夏季の降水量と豪雨の頻度が近年増加傾向にあること、それによって洪水や土砂災害の被害が増加する可能性があることを報告しています。また温暖化による気温の上昇は、山頂部における凍結融解を助長させたり、融雪を早めたりすることで、地形変化や水・土砂流出を促進すると考えられています。
(中部山岳地域を対象とした研究の意義)
本事業が対象とする中部山岳地域では、周極地域と同様に地球規模の環境変動の影響をうけやすい地域であることが知られています。中部山岳の複雑な地形・地質や気候の条件はバラエティに富んだ研究の場を提供してくれます。また、利根川、信濃川など重要な河川の源流に位置し、下流に存在する都市域に水資源の供給源となります。中部山岳地域における研究によって、温暖化への対応策を講じる上で有意義な知見を得ることができると考えられます。
水循環・物質循環変動グループでは、水文学、砂防学、地形学、雪氷学、衛生工学などさまざまな見地から、温暖化・気候変動が水循環・物質循環に及ぼす影響を明らかにすることを目的として、研究を進めています。
進行中の研究
下図は、2010年度年次研究報告会において発表された研究を、対象とする現象とスケールに着目して分類したものです。研究グループの構成員の専門分野は幅広く、それぞれの研究者によって対象とする標高帯,空間スケールが違います。また、各スケールにおける各現象はそれぞれが相互に作用しており、明確に区分することは困難ですが、事業を進めていくうえで、各構成員の成果の中から一般化できる知見を抽出し、それらの関係性をあきらかにすることは本グループの重要な課題です。
今後の方針
標高に注目した研究
中部山岳地域では、わずかな水平距離の違いで大きな標高差があらわれ、それに応じて、寒帯から温帯まで幅広い気候帯が分布しています。標高軸に注目した空間変動に関する研究により,気候変動に伴う水・物質循環の時間変動を評価できます。現在までに、山岳域における気温逓減率や水の安定同位体比など、標高の違いによる違いが定量化されつつあります。今後、今までに得られている知見を拡充したり、他の観測項目を加えたりすることで、観測体制の拡充を図っていきます。
共有できるデータの収集
各構成員が取得したデータに加えて、機構内外で取得された使用可能なデータを援用することで、現象をより効率的にかつ深く理解することができます。気象観測や水質・流量などのデータを掲載したデータベースなどの情報を共有・活用することで、効率的に研究を進めていくことができます。
また温暖化の影響を評価するためには、過去に行われた研究を整理することも重要です。当事業に参加する機関では、中部山岳地域における研究が継続的に行われており、相当の研究成果が蓄積されています。中には、温暖化・気候変動の影響評価に直結するデータが含まれています。そうしたデータと比較可能なデータを観測・調査により取得することで、長期的な変化傾向を知ることができます。
雪の観測のネットワーク作り
中部山岳地域では、降雨にもまして降雪によってもたらされる多量の降水が水資源として極めて重要です。地球温暖化とそれにともなう気候変動は降雪の量や空間分布、融雪のタイミングを変化させる可能性があります。また、中部山岳地域外の流域を対象とした既往研究では、融雪期に渓流水のpHが低下するなど、渓流水質が融雪水によって影響を受けることが示唆されています。雪としてもたらされる水の挙動に対する理解を深め、その影響を明らかにするため、組織的で継続的な観測が不可欠です。
水質観測ネットワーク
水循環の解明は、当グループの基礎となります。水文学の分野では、ケイ素や塩化物イオンなどの溶存物質濃度に基づいて水の起源や流動経路を明らかにするという研究が行われてきました。近年では水の同位体(2H、18O)をトレーサーとして用いる研究が盛んに行われています。これらの手法を組み合わせることで、より精確に現象を解明が期待されます。水によって輸送される硝酸態窒素や酸性降下物などの汚染物質の挙動を把握することも重要な課題です。左の地図は本事業における降水・河川水の採取地点を示しています。今後、採取地点を追加し、より広く、より密な水質観測ネットワークを作っていきます。