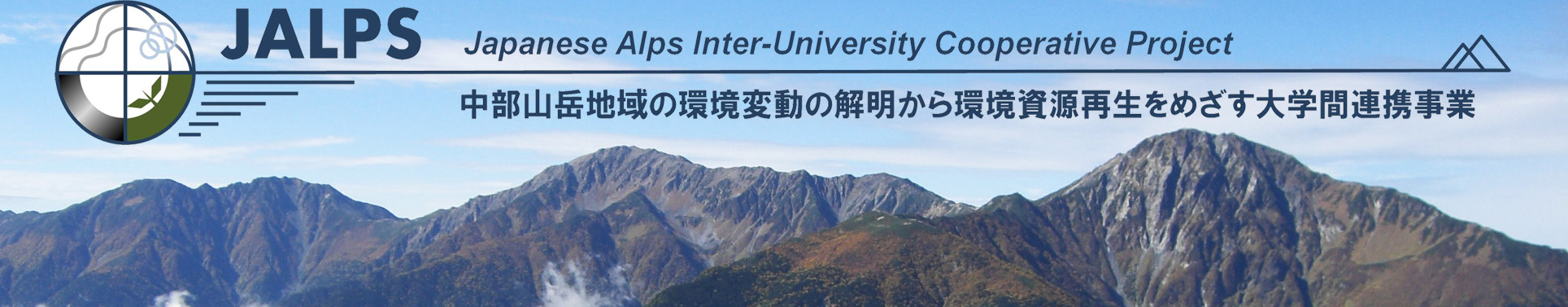
2011�N12��16-17���M�B��w�ɉ����ĊJ�Â���܂����N��������̔��\�v�|�ł�
| CM1�@ |
���R�����n�ł̋C�ۊϑ��f�[�^�̌��J �ʐ��Y�@�i��w |
| �@ | |
| CM2�@ | �����R�x��̒n��C��ω��\���Ɍ������ۑ�Ə����� �ጎ�F�i�}�g��w�j |
| �@ | |
| CM3�@ | �ċG�̒����R�x�n��Ŋϑ����ꂽ���̓��ω� ��쏃���E��쌒��i�}�g��w�j |
| �@ | |
| CM4�@ | ���������̊ϑ��f�[�^�Ɍ���C��ϓ� �����@��E��쌒��i�}�g��w�j |
| �@ | |
| CM5�@ | �A�W�A�����X�[���̕ϓ������Ƃ����ËC���Ɖ��g�������̐ړ_ �A�c�G���i�}�g��w�j |
| �@ | |
| CM6�@ | ���{�̍~��ϓ����K�肷�鉓�u���� �ؕ����L���E�A�c�G���E���m�h�i�}�g��w�j |
| �@ | |
| CM7�@ | ���V�������i��6000�N�O�j�̉ċG�A�W�A�����X�[���̕ϗe �g�ǐ^�R�q�E�A�c�G��(�}�g��w) |
| �@ | |
| CM8�@ | �����R�x��ɂ����鑍�ϋK�͏�̕ϓ��v���@-�̈�C�f���ƑS���C�f���̉��p- �g�c�����E�A�c�G��(�}�g��w) |
| �@ | |
| CM9�@ | ���ؔN�ւɊ܂܂��_�f���ʑ̔��p�����C�� ��c�q��(�M�B��w)�E���ˁ@���E�����K�i���É���w�j�E���]�@�P�i�M�B��w�j |
| �@ | |
| CM10�@ | �z�K�n��ɐ��炷��L�t��3����̋C�� ���c�I�j�E���]�@�P�i�M�B��w |
| �@ | |
| CM11�@ | �g��ɂ�����X�M�̔N�֕��ƋC��v�f�Ƃ̊W ���� �D�E���x����E���]�@�P�i�M�B��w�j |
| �@ | |
| CM12�@ | �k�C���A����A�{��ɐ��炷��J���}�c�̌`���w�����ƋC���Ƃ̊W �a�c�S���E���]�@�P�i�M�B��w�j�É�M��E���C�O�i��B��w�j |
| �@ | |
| CM13�@ | �㍂�n�̉ߋ�12000�N�Ԃ̒n�`�ƐA���̕ϑJ �͍����S���E���R�@�q�i�M�B��w�j |
| �@ | |
| CM14�@ | �؍�Α͐ϕ����̗L�@���ʂ͉��Ɏx�z����Ă��邩 �|�C��w�W�Ƃ��Ă̗L�@�Y�f�ʂ̈Ӗ��̍Č����| ���Ўq�E���c���ߎq�E�����x�m�v�i�M�B��w�j |
| �@ | |
| CM15�@ | �S�L�@�Y�f�ʂ�p�����A���{�C�ɂ�����ߋ�10���N�O�܂ł̋C��ϓ��̉�� �m���@��i�M�B��w�j |
| �@ | |
| CM16�@ | ���i�Β��l���CBIW07-5�R�A�̗��x�g������݂��ߋ��S���N�Ԃ̋C��ϓ� ���c���N�i�M�B��w�j |
| �@ | |
| CM17�@ | ���i�ΌΒ�͐ϕ�(BIW07�R�A)�̑S�L�@�Y�f�E�S���f�ܗL�ʕϓ��Ɋ�Â��ߋ�4.7���N�Ԃ̋C��ϓ��̉�� �؉z�q�F�E�����x�m�v�i�M�B��w�j�E�I�R�w�l�i���É���w�j |
| �@ | |
| CM18�@ | ���i�Α͐ϕ�BIW08-B ��TOC �ܗL���Ɋ�Â�24.7 ���N�O����14.5 ���N�O�܂ł̌ËC�� ���@�E��E�����x�m�v�i�M�B��w�j |
| �@ | |
| CM19�@ | ���i�ΌΏ��͐ϕ��R�A�iBIW08-B�j�Ɋ܂܂��ߋ�30 ���N�Ԃ̌]�����ΌQ�W�ϓ� �i���_��E�����x�m�v�i�M�B��w�j |
| �@ | |
| CM20�@ | ���t�L�t���уL���m�s�[�̌��������Y�͂̃����[�g�Z���V���O �����T�R�i��w�j�E��c�@���i�}�g��w�j�E�i��@�M�i�C�m�����J���@�\�j�E�{���@�B�i�F���q���J���@�\�j�E �֓��@��i��w�j�E�ލ������Y�i�}�g��w�j�E�O�}�M�q�i�������������j |
| �@ | |
| CM21�@ | Functional consequences of differences in canopy phenology for the carbon budgets of two cool-temperate forest types: simulations using the NCAR/LSM model and validation using tower flux and biometric data SAITOH Taku M. (Gifu Univ.) �CNAGAI Shin (JAMSTEC)�CYOSHINO Jun, MURAOKA Hiroyuki (Gifu Univ.)�C SAIGUSA Nobuko (NIES)�CTAMAGAWA Ichiro (Gifu Univ.) |
| �@ | |
| CM22�@ | �����A���[�T���ɂ�蔻�������㍂�n�̒n�`���B�j ���R�@�q�i�M�B��w�j�E�����B�Y�E �с@�v�v�i�W�I�b�N�X�R���T���^���g�j�E�����K�L�i�Z�z�����J���j�E �I���[�j�i�n�������R���T���^���g |
| �@ | |
| CM23�@ | �㍂�n�ɑ��݂��銈�f�w�ɂ��� ���@�āE���R�@�q(�M�B��w) |
| �@ | |
| CM24�@ | �����f�w�̏Ċx�k���� ����@���E���R�@�q�i�M�B��w�j |
| �@ | |
| CM25�@ | �R�x�n�`������Â����̕��������|�k�A���v�X�E���x���Ɂ| ���L�@�d�E���R�@�q�i�M�B��w�j |
| �@ | |
| WM1�@ | �㍂�n����ѐz�K�ɂ������C���������Z�x�̋G�ߕω� �@ �����I���Y�E�R�c�q�ƁE�{���T��E���X�ؖ��F�E��،[���i�M�B��w�j |
| �@ | |
| WM2�@ | ���쌧�ɂ����鉻�w���������̒n�捷 �@ �R�c�q�ƁE�{���T��E�R�{�듹�i�M�B��w�j |
| �@ | |
| WM3�@ | �����R�x�n��ɂ�����~�����ʑ̃}�b�v�Ƃ��̌��� �@ �q��T�I�E�e�R�`�j�i�}�g��w�j�E�ێR�_��i�R�������j�E�R���@�i�}�g��w�j�E��،[���i�M�B��w�j |
| �@ | |
| WM4�@ | �����R�x�n��ɂ�����~�����蓯�ʑ̑g���̎���ԕϓ����� �@ �e�R�`�j�E�q��T�I�E�R���@�i�}�g��w�j�E��،[���i�M�B��w�j�E�����i�}�g��w�j�E�ё��N�v�E��ˏr�V�i��w |
| �@ | |
| WM5�@ | �����R�x�X�ш�͐�ɂ�����L�@�����ԂƔ����������� �@ �R�c�r�Y�E���c�����E�������E���ݔ����E��ؐ����E���x���E��ˏr�V�E�A������q�E�ё��N�v�i��w |
| �@ | |
| WM6�@ | �㍂�n�n��ɂ�����N���̐������� �@ ���������E���R�@�q�i�M�B��w�j |
| �@ | |
| WM7�@ | �㍂�n�ɂ�����N���̓����ɂ��� �@ �q�����V�E���X�ؖ��F�E�ҁ@�ꐬ�E��،[���i�M�B��w�j |
| �@ | |
| WM8�@ | �������n�ɂ�����n�\���̏Ɏ_�Z�x�ƒ��f�̓��� �@ ����āi�}�g��w�j |
| �@ | |
| WM9�@ | �L�l�}�e�B�b�NGPS���ʂɂ��k�A���v�X���J�ɂ�����ϐ�[�̊ϑ� �@ ���X�ؖ��F�Eꠁ@��o�E��،[���i�M�B��w�j |
| �@ | |
| WM10�@ | ���n�x���R�тŔ��������R�Ύ����n�\���ɋy�ڂ��e�� �@ ���X�ؖ��F�i�M�B��w�j�E�r�c�@�ցi�}�g��w�j�E���J���F�i��C��w�j�E��،[���i�M�B��w�j |
| �@ | |
| WM11�@ | �x�m�R�ɂ�����i�v���y�̒��ڊϑ��J�n �@ �r�c�@�ցi�}�g��w�j�E��ԁ@���i�k�C����w�j�E���g�N�Y�iJAMSTEC�j |
| �@ | |
| WM12�@ | �d�C�T����p�����d�͐��ό`�n�`�̓����\���̐���@�|�����R�x��̑͐ϊ�R�n��ΏۂƂ��ā| �@ ����Ŏq�E�r�c�@�ցi�}�g��w�j |
| �@ | |
| WM13�@ | ��A���v�X���R��ł̊�Քj�ӁE�y�����Y�̊ϑ� �@ �������m�i�}�g��w�j |
| �@ | |
| CC1�@ | �Ɏ_�Ԓ��f�Z�x�̈قȂ�2�̏��k����ł̒��f���Ԃ̔�r ���c�S���E�����m���E�����@���E�˓c�C�d�i�M�B��w |
| �@ | |
| CC2�@ | ���f�E�����Y�����X�ѓy��̌ċz�����ɗ^����e�� �����@���E�����R���q�E�˓c�C�d�i�M�B��w |
| �@ | |
| CC3�@ | �W���X�x�ɂ������X�ѐ��Ԍn�̒Y�f���x�Ɋւ����b�I���� ��{�����E�����k��i�M�B��w�j |
| �@ | |
| CC4�@ | �q�m�L���т̓y�뒂�f���@���ɉe��������ڂ��v�� �א�ށX�}(�M�B��w)�E�ɓ����i����X�ёg���j�E���с@���i�M�B��w�j�E����h�O�i�X�ё����������j |
| �@ | |
| CC5�@ | �q�m�L���т̎Ζʏ㕔�Ɖ����ɂ�����y��ċz�̋G�ߕω� �����ꑾ�E�א�ށX�}�E���с@���i�M�B��w�j�E����h�O�i�X�ё��������� |
| �@ | |
| CC6�@ | �J���m���u�i���n�тɂ�����y�댗�L�@�����ԁ@�|�M���b�v���U�C�N�\�����l�����ā| �ё��N�v(��w)�E�A�c�@�[(�}�g��w)�E ��c�G�s(�M�B��w)�E ��ˏr�V(��w) |
| �@ | |
| CC7�@ | Carbon cycling in an old-growth forest: �唒��u�i������ ��ˏr�V�E����T��Y�E �ё��N�v�E �u�×f�q�E��������E�����R��(��w) |
| �@ | |
| CC8�@ | �X�M�l�H�тɂ�����ї�Ɠy��ċz�ʂ̊W ���@�A�N�E����T��Y�E ��ˏr�V(��w) |
| �@ | |
| CC9�@ | �唒��ɑ��u�i�тɂ�����y��ċz�̋�ԓI�ϓ� �u�×f�q�E����T��Y�E ��ˏr�V(��w) |
| �@ | |
| CC10�@ | �≷�ї��t�L�t���тɂ����钂�f�z�� �X�c�I��E�ё��N�v�E ��ˏr�V(��w) |
| �@ | |
| CC11�@ | ���t�L�t�����n�т���є��̒n�ɂ�����T�T�Q�����y��ċz���x�ɗ^����e�� ����T��Y�E�u�×f�q�E���������E��ˏr�V�E�ё��N�v(��w)�E���@�P�J (National Park Research Institute)�E����@��(����c��w�j |
| �@ | |
| CC12�@ | Landsat�f�[�^�𗘗p����LAI���z�}�̎��� �����P�Y�i��w�j |
| �@ | |
| CC13�@ | NPP estimation of cropland and abandoned cropland using biomass sample field spectra and field meteorological data Hasan Muhammad Abdullah (Gifu University)�C Tsuyoshi Akiyama (ProfessorEmeritus)�C Michio Shibayama (NIAES) �C Yoshio Awaya (Gifu University) |
| �@ | |
| CC14�@ | �����̑����ł̉��g�������F�ϐ�[�A�o�C�I�}�X�A�퐔�̕ω� ��@���i�}�g��w�j |
| �@ | |
| CC15�@ | �����R�x�n��тɂ�����Y�f�z���� �J���m���u�i���n�тɂ�����Y�f�����̏�Ƃ��Ă͎̌��ɂ��� �A�c�@�[(�}�g��w)�E�ё��N�v�E����T��Y�E�u�×f�q�E��ˏr�V(��w)�E����b����(�}�g��w)�E��c�G�s�i�M�B��w�j |
| �@ | |
| CC16�@ | �W���̈Ⴂ�ɂ�郌���Q�c�c�W�̐A�����z�ƌ���������ы����ۂɂ��ۍ��`���ɂ��� ���� �G�l�i�}�g��w�j�E�L�� ��i���{��w�j�E�A�c �[�i�}�g��w�j |
| �@ | |
| CC17�@ | ��ΐj�t���тƐj�L����т̗я��A���̌Q�W�\���Ɣ����̔�r �n粊E�A�c�@�[�i�}�g��w�j |
| �@ | |
| CC18�@ | �ሳ�����ł̌`�ԕω��ɂ������������̉� ����b���ށE�{���V��E���c�`�F�A�c�������i�}�g��w�j�E�x���@���E�������i�������������j�E�A�c�@�[�i�}�g��w�j |
| �@ | |
| CC19�@ | �����̃R�P�A�����̕ϑJ�`40�N�O�ƌ��� �x�@����i��s��w�����j�E��@���E�o��m��i�}�g��w�j�E����N���i��s��w�����j |
| �@ | |
| CC20�@ | ���쌧�ɂ�����J�[�{���E�I�t�Z�b�g��O��Ƃ��������p�ђn�c�ނ̃o�C�I�}�X�G�l���M�[���p�Ɋւ����b���� �|�����R�x�n��̖����p�ђn�c�ނɂ��J�[�{���X�g�b�N�ʂ̎Z��| ����͌�E���ǐ��E�����G�I�E�n�ӌ����i�M�B��w�j |
| �@ | |
| CC21�@ | ���쌧�Y�؍ނ̃��C�t�T�C�N���A�Z�X�����g����������Ղ���Y�f�z�� ����3�X�M�A�J���}�c�A�A�J�}�c�A�q�m�L�̃J�[�{���o�����X�̎Z�o �R�`����E���ǐ��E�����G�I�E��ˌ��M(�M�B��w) |
| �@ | |
| ES1�@ | �����R�x�n��ɂ�����V���N�V�P�A���̍��x���z�ɂ�������`�I�n���̂��ݕ��� ��c�����E�����N��E���דl�E�ց@�Ȉ�E���{�W��E�s�엲�Y�i�M�B��w�j |
| �@ | |
| ES2�@ | �����A�u�����V�ɂ��A���ւ̉��w�[�� �����^���Y�E�s�엲�Y�i�M�B��w�j |
| �@ | |
| ES3�@ | �㍂�n�ɂ�����}���n�i�o�`��6��̉ԗ��p�`�Ԃ̕ψقƋG�ߔ������� �k��m���E�]��@�M�E�s�엲�Y�i�M�B��w�j |
| �@ | |
| ES4�@ | �����R�x��ɂ�����T���V�i�V���E�}��3�����^�̈�`�I�����̌��� ��ڐ��ԁE�s�엲�Y�i�M�B��w�j |
| �@ | |
| ES5�@ | �R�x��ɂ�����E�c�{�O�T�̉ԃT�C�Y�ƖK�ԃ}���n�i�o�`���̏ꏊ�ԕψ� �I�J���Ǝq�E�s�엲�Y�i�M�B��w�j |
| �@ | |
| ES6�@ | �����R�x��ɂ����郄�}�z�^���u�N���̕W���ԂŌ����ԃT�C�Y�ψقƈ�`�q���� ����S��E�s�엲�Y�i�M�B��w�j |
| �@ | |
| ES7�@ | �����F���������Ȃ��^�Љ�A�u�����V�ɂ�����Љ�ێ��@�\ �����@�[�E�s�엲�Y(�M�B��w) |
| �@ | |
| ES8�@ | �����M�n���V��Q�̐F�ʓ�^�̕p�x�̒n�����z�Ƃ��̔N���ϓ� ��菇���E���R�×Y�i�M�B��w�j |
| �@ | |
| ES9�@ | �O���A���G�]�m�M�V�M�V�Ƃ��̋߉��ݗ���m�_�C�I�E�Ƃ̎G��`���@�|�`�Ԃƕ��z�̔�r�| �H�������E�����k��i�M�B��w�j |
| �@ | |
| ES10�@ | �q�Q�i�K�J���g�r�P���������̕��q�n���n���w�I�����@-������ŗL�̐V��u���}�q�Q�i�K�J���g�r�P���v�̔���- �����T��i�M�B��w�j�E�q���Lj�i��t���������فj�E����K���i�M�B��w�j |
| �@ | |
| ES11�@ | �R�x������ɌŗL�̌��n�I�����ނ�ΏۂƂ������q�n���n���w�I���� �����Y�o�E�{���@���E��숟��E����K���i�M�B��w�j |
| �@ | |
| ES12�@ | ���A�W�A�n��ɂ�����^�i�S���ȃA�u���{�e�����ނ̌n���n�� ���ь���E�גJ�a�C�i�ߋE��w�j�E�{��~��i�R����w�j�EKim Chi-Hong�i�؍��������Y�Ȋw�@�j |
| �@ | |
| ES13�@ | �`���J�Q���E�ɂ������`�I�\���@�|�R�n�����n�܂ŕ��L���������z����W�F�l�����X�g��ɒ��ڂ��ā| �֓����G�E����K���i�M�B��w�j |
| �@ | |
| ES14�@ | �R�I�C���VAppasus ��2 ��̌n���n���w�I�����@�|�R�x�`���ɂ���`�q�������f���̌���- ��ؒq��E�J�V�@���E����K���i�M�B��w�j |
| �@ | |
| ES15�@ | �R�x�������X�J�V�V���A�Q���h�L�̌`�ԓI���^�l���ɂ����镡�G�Ȑi���j�i�����j:�V���A�Q���V��, �V���A�Q���h�L�ȁj ��ؒq��i�M�B��w�j�E��ؐM�v�i���{���q�̈��w�j�E���c����Y�i�}�g��w�j�E����K���i�M�B��w�j |
| �@ | |
| ES16�@ | �I�u�W�F�N�g�x�[�X��p�������R�A���̕��ށ@�|�k�A���v�X��O�x������Ƃ��ā| ���V�M���E�������l�i�M�B��w�j |
| �@ | |
| ES17�@ | �����̉q���摜�ɂ��㍂�n�̐A����͂̔�r �����^�����E�������l�i�M�B��w�j |
| �@ | |
| ES18�@ | ���W�R���w���R�v�^�[��p�����M�B��w�_�w���\�����K�їѕ��ސϐ���ɂ��� �����D���E�������l�i�M�B��w�j |
| �@ | |
| ES19�@ | ��Ŋ뜜�V�W�~�`���E�ނ̌̌Q�����Ɋւ��錤�� �]�c�d�q�E�������u(�M�B��w) |
| �@ | |
| ES20�@ | ��Ŋ뜜��~���}�V�W�~�̉a�I���ƎY���I�D���Ɋւ��錤�� �����G���E�]�c�d�q�E�������u�i�M�B��w�j |
| �@ | |
| ES21�@ | �M�B��w�_�w������K�тɂ�����V�f���V�Q�W�̐������z ����F���E�É��@�ȁE�X�J�_�V�E�������u�i�M�B��w�j |
| �@ | |
| ES22�@ | ��k�A���v�X�̗Ő��Ƃ��Ԕ��̃`���E�@�|���j�^�����O�T�C�g1000���R�ђ����| �R���@�m�E�]�c�d�q�E�������u�i�M�B��w�j |
| �@ | |
| ES23�@ | ���уA�J�}�c�тɂ�����6�N�Ԃ̊O���ۍ��o�C�I�}�X�ϓ��ƋC�ۈ��q�̊W ���c�c��E�R�c���`�i�M�B��w�j |
| �@ | |
| ES24�@ | ���ъ����ɐ��炷��q�m�L�ƃT������p���̎����` ��J�����E���с@���i�M�B��w�j�E����B�V�i�}�g��w�j |
| �@ | |
| ES25�@ | �f�W�^���J�����ƃX�L���i�[��p�����q�m�L�����̃V���[�g�t�F�m���W�[����ьt���������̊ϑ� ����@���E���с@���i�M�B��w�j�E�R�{�ꐴ�i���É���w�j�E����q�i�������������j |
| �@ | |
| ES26�@ | ����K�тɂ�������������n�ߗނ̎�g���Ƌ�ԕ��z ��v�ۈ��i�M�B��w�j�E�c�������i�}�g��w�j�E�r�c�j�l�E�������K�i�M�B��w�j |
| �@ | |
| ES27�@ | �����R�x�n��̍��R�A�����ɂ����镪�z�^�g�� �����@�́i�}�g��w�j |
| �@ | |
| ES28�@ | �~���}�n�^�U�I�̊��K����S����`�q�̃X�N���[�j���O �����@�́E���c�`�F�i�}�g��w�j�E�����i��p�j���b�i�`���[���q��w�j�E���X�@���i�����H�Ƒ�w�j |
| �@ | |
| ES29�@ | ����K�сE�X�ь��E���ɂ����鉷�g�������F���g�����u�̌��ꌟ�� ���䗲���E���ؑ�S�E�c�������i�}�g��w�j�E���с@���i�M�B��w�j |
| �@ | |
| ES30�@ | �ؑ]��x3�N�Ԃ̐A���ω� ���숻�q�i�}�g��w�j |
| �@ | |
| ES31�@ | ���������̃X�X�L�ɔF�߂�ꂽ�V�a�Q�̕a���ہi�q�X�ہj�ɂ��� �o��m��E��@���i�}�g��w�j�E��ؒq�V�i��s��w�����j�E�ז�@���i�����Ȋw�����فj |
| �@ | |
| ES32�@ | �≷�ѓтɂ�����A���Q�W�̋�ԕ��z�ƑJ�ڂ̐����I�A�v���[�` ���͉Ö��E�A�c�@�[�i�}�g��w�j�E���K�iNIAES�j |
| �@ | |
| ES33�@ | �W�����\�A���~���}�n�^�U�I�̓K���@�\�F���ԁE�����E��`�q �c�������E���c�`�F�E�����@�́i�}�g��w�j�E�R�c�@���i���M��w�j�E�i��@�� �E�R�������E�H���@�m�i���s��w�j�E���с@���i�M�B��w�j |
| �@ | |
| ES34�@ | �v�������Ɋ�Â������R�x��ɂ����郄�}�l�̖ڌ��� ���R���T�E��e���j�i�}�g��w�j |
| �@ | |
| ES35�@ | �����͂ɂ�郄�}�lGlirulus japonicus �̐H�� �����ؒm���E��e���j�E�ʖ،b�����E���R���T�i�}�g��w�j |
| �@ | |
| ES36�@ | ���}�lGlirulus japonicus �̋x���ꏊ�̑I�� �ʖ،b�����E��e���j�E�����ؒm���E���R���T�i�}�g��w�j |
| �@ | |
| ES37�@ | �PKITE �u�PK �����g�����X�N���v�g�[���i���v���W�F�N�g�v�@�|�����ނ̍����n���̉𖾂�ڎw���ā| ���c����Y�i�}�g��w�j |
| �@ | |
| ES38�@ | ����P�x�ɂ�����X�m�L���A���̍��������یQ�W�̕W���Ԕ�r �L���@��i���{��w�j�E�o��m��i�}�g��w�j |
| �@ | |
| ES39�@ | �k�A���v�X�ɂ�����R�}�N�T�̐����T���@�|���ϓ��w�W�̊�b�f�[�^�����| �n��獁�q�E�k���t�́E�X�@�D���E���R�@�q(�M�B��w) |
| �@ | |
| ES40�@ | �R���W���ɂ����ƂƗ��R�ї��p�ɂ��Ă̌����@�|���쌧�k���܌S���n���k��S��ΏۂƂ��ā| ��c仍]�E�y�{�r�a�E��c�G�s�i�M�B��w�j |
| �@ | |