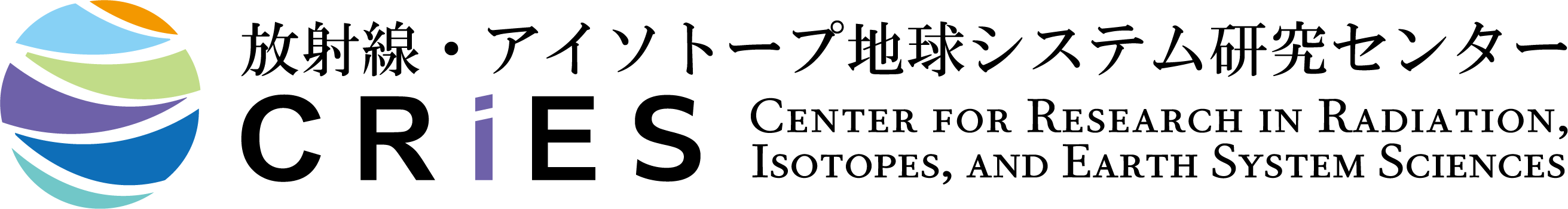アイソトープ環境動態研究センター環境動態予測部門(旧陸域環境研究センター)では,地表面における水と熱のエネルギーの交換の諸過程を明らかにすることを目的に,熱・水収支観測圃場における長期連続観測を続けています.
観測圃場説明会資料
平成27年5月13日(水)に行われた観測圃場説明会の資料です.
熱収支・水収支観測圃場概要
観測圃場は,世界測地系(WGS84):36°06′49″N (36.1135), 140°05′42″E (140.0949), 日本測地系(Bessel): 36°06′37″N (36.1103), 140°05′53″E (140.0982),標高27.0mに位置し,直径160 m(面積約20,000m2)の円形で,その外周は圃場からの表層流出水を観測するためのコンクリート製の側溝に取り囲まれています.1975年の観測開始時には,中心部が外周側溝の天端高度より約0.5m高くなるように盛土をし,1/160の平均勾配で表層水が側溝に集まるように整地されていました.その後,1988年に圃場土壌の転地換えを行い,現在ではほぼ平坦になっています.観測当初,地表面は牧草でしたが,現在は多種の雑草が混在する草原となっています.また,圃場内の植生を均一に保つための草刈りを毎年夏,秋に行っています.
圃場内は,蒸発散測定のためのライシメーターや高さ30mの気象観測塔及び地下水位観測井等の施設の他,本観測システムのための各種諸測器が配置され,測定値は研究棟のデータ集録室で記録・収録されています.
熱収支観測システムでは,超音波風速温度計で運動量と顕熱のフラックスを直接観測しているところが特色です.一方,水収支観測システムでは,秤量式(ウエイング型)ライシメーターによって高精度の蒸発散量を連続測定しているところに特色があります.以上のようにして,圃場内に出入りする熱・水収支の各要素を,できるだけ独立した測器で計測し,得られたデータを資料集として刊行しています.
これらのデータの一部は,「現在の気象・水文測定値」(5分ごとに更新)として,ホームページ上で公開しています.また,本日の時系列図,最近5日間の時系列図もホームページ上で見ることができます.
熱収支・水収支観測圃場 ルーチン観測項目
以下の項目がルーチン的に24時間365日測定されています.
一般気象
- wind direction
- wind speed at 1.6 m (m/s)
- wind speed at 12.3 m (m/s)
- wind speed at 29.5 m (m/s)
- air temperature at 1.6 m (degreeC)
- air temperature at 12.3 m (degreeC)
- air temperature at 29.5 m (degreeC)
- dew point temperature at 1.6 m (degreeC)
- dew point temperature at 12.3 m (degreeC)
- dew point temperature at 29.5 m (degreeC)
- soil temperature at -0.02 m (degreeC)
- soil temperature at -0.10 m (degreeC)
- soil temperature at -0.50 m (degreeC)
- soil temperature at -1.00 m (degreeC)
- air pressure (hPa)
- sunshine duration (min)
放射
- shortwave radiation (W/m2)
- net radiation (W/m2)
フラックス
- soil heat flux (W/m2)
- momentum flux at 1.6 m (m/s)^2
- momentum flux at 12.3 m (m/s)^2
- momentum flux at 29.5 m (m/s)^2
- sensible heat flux at 1.6 m (degreeC m/s)
- sensible heat flux at 12.3 m (degreeC m/s)
- sensible heat flux at 29.5 m (degreeC m/s)
水文
- ground water level at -2.2 m (m)
- ground water level at -10.0 m (m)
- ground water level at -22.0 m (m)
- precipitation (mm/hour)
観測機器・観測方法
- 全天日射計・正味放射計
太陽から地表面に達する短波エネルギー及び地表面と大気間のエネルギーの出入りを測定します.近くに地温計と地中熱流板が埋設され,合わせて地中での熱移動を測定しています.
 全天日射計取扱説明書 [full (4.3Mb in PDF)] [selected (2.3Mb in PDF)]
全天日射計取扱説明書 [full (4.3Mb in PDF)] [selected (2.3Mb in PDF)]
- ウエイング・ライシメーター
地表面蒸発散量を測定するために,容器に土を詰め,それを地下室にセットした後,その表面を自然状態に復元して,蒸発散による水分減少量を直接重量測定します.(高さ2m).老朽化のため、2006年10月より運用停止.
- 気象観測塔
高さ30mの塔の3高度(1.6m,12.3m,29.5m)に超音波風速温度計,気温計,露点温度計が取り付けられています.
- 気温計・露点温度計
気象観測鉄塔に設置された通風式白金抵抗温度計,通風露点温度計によって,高さ30mまでの気温・湿度の垂直分布を知ることができ,接地逆転の研究などが行われています.
- 超音波風速温度計
超音波を利用して三次元的な空気の流れ,および温度を捉えることができ,運動量と顕熱フラックスも観測しています.
- 表面流出量測定装置
圃場周辺の溝に流入した表面流出水を集めて,堰を越流する水頭から表面流出量を測定します.
- 地下水位計
地下水位は2m,10m,22mの3深度で測定されています.それぞれの水位は深度2mの井戸が1~2m,深度10mの井戸が3?4m,深度22mの井戸では4?5m程度です.
- 蒸発パン・雨量計・雨量強度計
直径1.2mの円筒型容器中の水面変化から水面蒸発量を求めています.また,雨量は転倒升型雨量計および雨量強度計で観測しています.
 雨量計感部取扱説明書 [full (2.4Mb in PDF)] [selected (2.2Mb in PDF)]
雨量計感部取扱説明書 [full (2.4Mb in PDF)] [selected (2.2Mb in PDF)]
- 回転式日照計
日照時間を研究棟屋上につけた回転式日照計で観測しています.
- 4成分放射計
短波・長波放射計を上下に取り付けることで,4成分を独立に観測しています.
- 植生の状態
圃場表面を均一に保つために,ライグラスを主体とする牧草を播種してあります.春~秋にかけて約1m伸び,秋に一様な高さに刈ります.
- データ集録室
それぞれの測器で測定されたデータは約100m離れた研究棟に送られ,気象日報として保管されます.